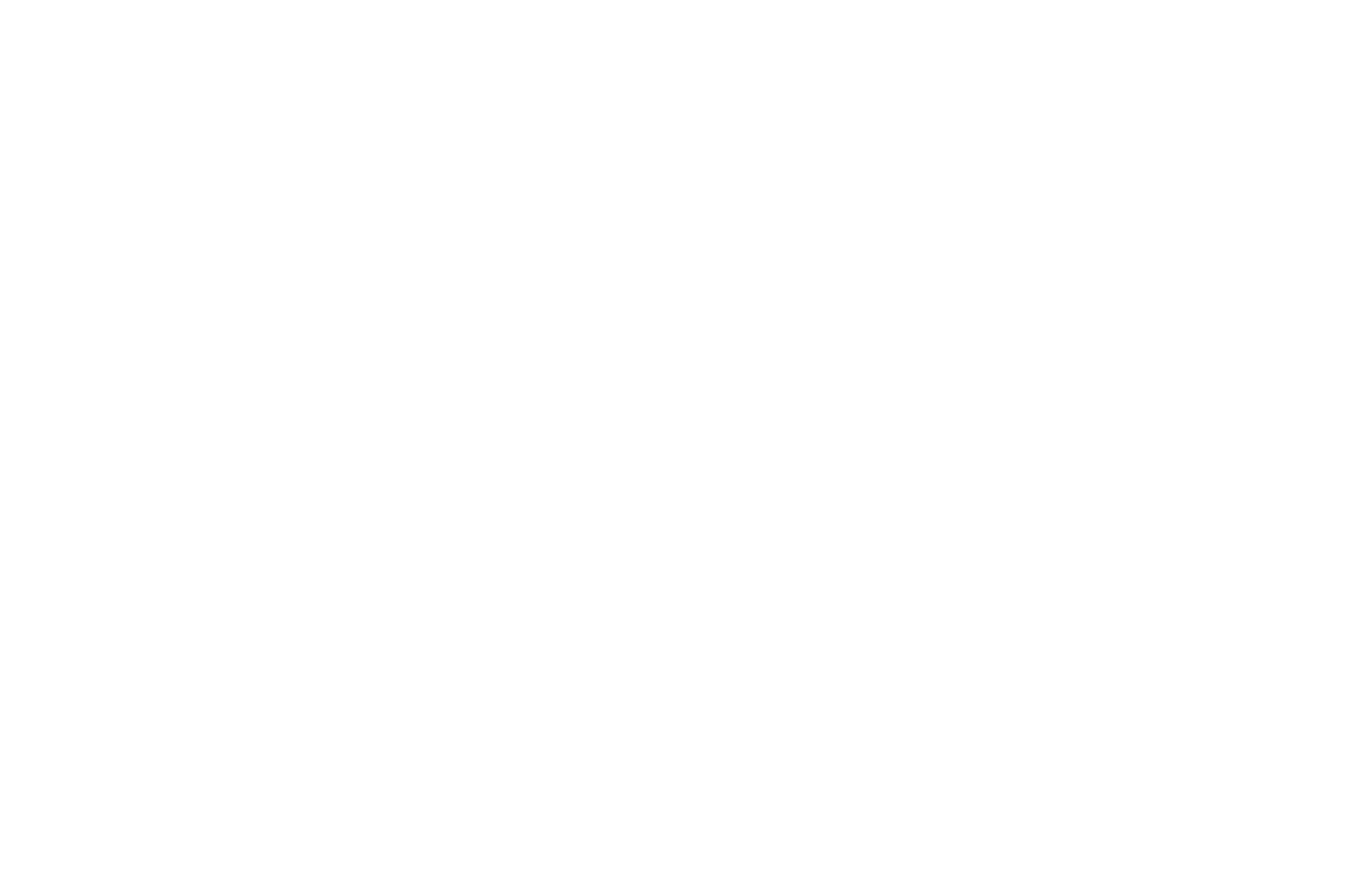[受賞]Good Design賞(日本) ACCブロンズ賞 iFデザイン賞(ドイツ) Red Dot design賞(ドイツ) 第六回日芸賞
[個展]2006年 水戸芸術館にて 松井龍哉展、2013年POLAミュージアムアネックスにて「花鳥間」展、
2014年伊勢せきやにて「Re:Play」展、 2017年よりヨーロッパ各地の美術館・博物館にて開催される巡回展”Hello,Robot”展に作品を出展中。
日本大学藝術学部客員教授、成安造形大学客員教授、早稲田大学理工学部非常勤講師、東京理科大学工学部非常勤講師、グッドデザイン賞審査委員(2007-14)